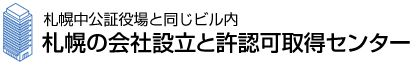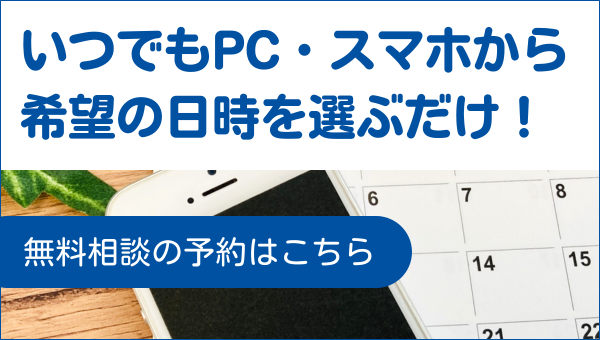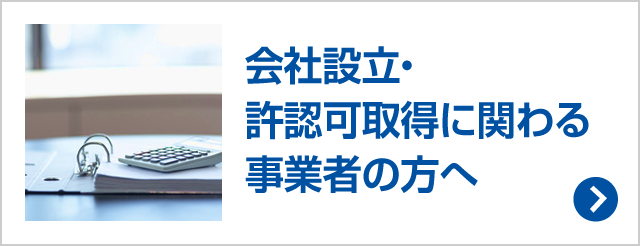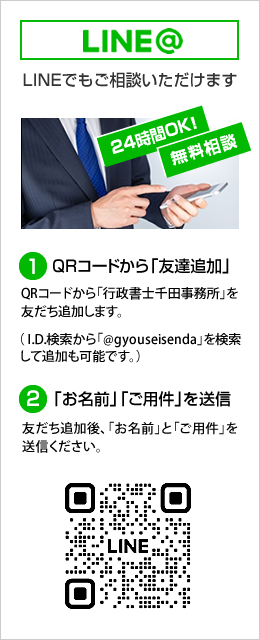古物とは一度使用された物品や使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に「幾分の手入れ」をしたものをいいます。
古物の区分
古物営業法施行規則第2条では、古物を13種類に区分しています。古物商許可の申請を行う際は、どの区分で営業を行うかを決める必要があります。
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
- 自動車(その部分品を含む。)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
- 自転車類(その部分品を含む。)
- 写真機類(写真機、光学器等)
- 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサ、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
- 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
- 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
- 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)
古物営業の形態
古物営業の形態は下記の3つに区分されます。
- 古物商 古物の売買・交換・賃貸を業として行うため許可を受けた者
- 古物市場主 古物市場の営業を営むため許可を受けた者(古物市場とは古物商間で古物の売買、交換する市場)
- 古物競りあっせん業(※1)
(※1)古物を売買しようとする者のあっせんのためインターネットオークションのシステムを提供する営業のことをいいます。
許可申請における欠格事由
古物商許可を受けるには以下の欠格要件に該当しないことが求められます。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
- 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
※古物営業法第4条より抜粋
許可証の携帯
古物商の許可を取ったら、以後の行商または競り売りをするときに必ず許可証を携帯するよう法で定められています。
(許可証等の携帯等)
第十一条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
※古物営業法より抜粋
個人宅に古物の買い受けに行く場合はもちろん、古物商が集まる古物市場に参加し取引を行う場合も、必ず許可証の携帯が求められます。各人の古物商許可番号や氏名などは古物市場主により記録され、「いつ、誰が、どの品物を売買したか」も記録されます。
標識の掲示
古物商の許可を得たら、許可証を常に携帯することに加え、営業所の見やすい場所に「国家公安委員会規則で定める様式の標識」を掲示しなければなりません。同規則に定められている様式の標識とは、次のようなものを指しています。
(標識の様式)
第十一条 法第十二条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第十三号若しくは別記様式第十四号又は次条第一項の規定による承認を受けた様式とする。
※古物営業法施行規則より抜粋
- 標識の材質は、金属やプラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するものであること
- 紺色地に白文字であること
- 許可証の番号を記載すること
- サイズは8㎝×16㎝であること
- 「○○○商」の「○○○」の部分には、営業所などで取り扱う古物区分を記載すること
- 下欄には、古物商の氏名又は名称を記載すること
※記様式第13号(第11条関係)参照
関係法令
手続先
所轄警察署長を経由して都道府県の公安委員会宛てに申請を行います。
【窓口】
所轄警察署生活安全課保安係(札幌は札幌方面各区警察署)
【手数料】
申請手数料:19,000円
古物商許可申請のサポートは当事務所行政書士へ
当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。